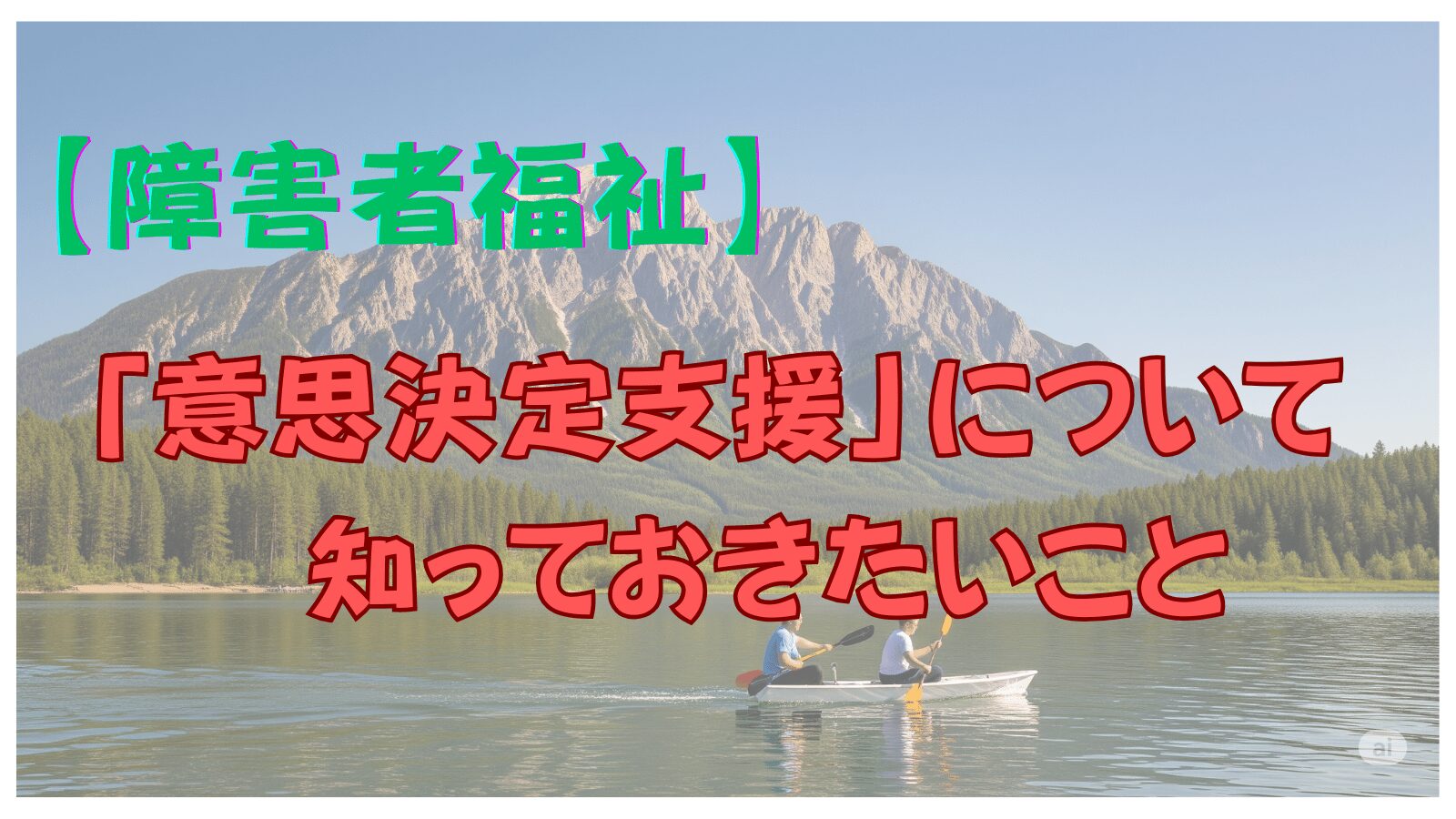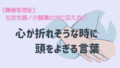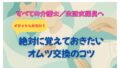障害者福祉における「意思決定支援」は、近年ますますその重要性を増しているキーワードです。
令和6年の報酬改定から、より明確に意思決定支援を評価する方向性が示されました。
それまでなんとなく耳にしていた言葉でも、「報酬改定にかかわる」と聞いた途端にざわつきますよね。僕が働いていた職場もそんな感じでした。
・ちゃんとやらないと減算されるの?
・なにをすればいいの?
・そもそも意思決定支援って、具体的にいうとどういうこと??

障害者福祉に携わる人間なら知っておきたい「意思決定支援」について、施設支援員歴18年の僕から、お伝えしたいことをまとめました。
結論から申し上げますと
「利用者の人権を尊重し、支援員としての仕事を日々しっかりと行っていれば、何の問題もありません」
でもその、「日々しっかり行う」のが難しいんですよね。できる限りわかりやすく解説していきますのでよかったらお読みいただけると幸いです。
意思決定支援とは
障害のある方が、自身の生活に関する様々な選択を、自らの意思に基づいて行えるようサポートする一連の取り組みを指します。
それは単に本人に必要な情報を提供するだけではありません。
・本人が理解しやすいように伝える。
・じゅうぶんに熟慮する時間を提供する。
・表明された意思を尊重し、実現に向けてともに歩む。
そのプロセス全体を指します。
その根底には、「障害のある方も一人の人間として、自己決定の権利を持つ」という基本的な考え方があります。
日々の食事や服装といった些細なことから、住まいや仕事、人間関係、将来設計…といった重要な事柄に至るまで、自身の人生を自らの意思で選択し、決定する権利を保障するものです。
適切な意思決定支援は、障害のある方の自律的な生活を支え、自己効力感を高め、生活の質(QOL)の向上に不可欠です。本人が主体的に選択に関わることで、サービスへの満足度や生活への意欲も向上しより豊かな人生を送ることが期待されます。

僕たちも日々、あらゆる局面で自己決定をして生きているわけですから、障害のある方にもその権利を保証しよう、ということです。
意思を拾うことが難しい方へのアプローチ
ここまで読んで、日々忙しく支援業務に追われている皆さんの中には
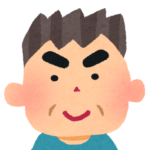
いかにもお役所が考えそうなキレイゴトだぜ!
現場の実態をわかっちゃいねえ
と思う方もいるかもしれません。
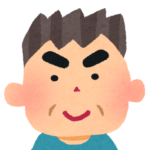
重度の重複障害や知的障害の方など、意思を発信するのが難しい人だっているだろ!
僕もはじめはそう思いました。
しかし、重要なのは「どんなに障害の重い方でも、意思はある」ということ。
寝たきりで、呼吸器につながれ、ほとんど意思の疎通が難しいように見える方であっても、されたら不快に感じることや、逆に良い気分になることはあるはずです。
これは嬉しい、これは嫌、言語化できないとしてもそう感じること自体が「意思」です。
それを大前提としてわかっておくことが基本になります。発信することが難しいだけで、じつは頭の中ですごくいろいろなことを考えている方だっています。
言葉によるコミュニケーションが難しい場合、本人の意思をどのように理解し、尊重するのか?
支援における大きな課題です。
絵やカードの提示、触覚や視覚への刺激など、さまざまなコミュニケーション手段を試みることが重要になります。
ただし、ここには大きな落とし穴があります。
さまざまなコミュニケーション手段を試みることは大事なのですが、その「やってる感」で職員が満足してしまいがちです。これは現場あるあるです。
経験ないでしょうか??
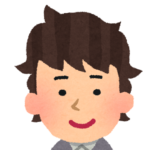
〇〇さんはAとBどっちがいいんだろう

絵カードをみせて選んでもらおう
→ 偶然動いた手がAのカードに触れる
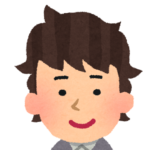
Aだね。Aってことでいいね。
何もしないで勝手に決めてしまうよりは、意思確認のためのコミュニケーションを取ったことは評価されてもいいかもしれません。そこから関係性が広がり、よりその方の理解へとつながることは考えられます。
しかし、日中活動のちょっとした場面ならまだしも、その方の人生にかかわる重要な決定をこのようなやり方で「本人の意思」と結論づけてしまうのは大変危険です。
その反応が本当に本人の意思に基づいているのか、偶然の動きや生理的な反応ではないのかを慎重に見極める必要があります。
単一の反応だけでなく、様々な状況下で繰り返し観察し、一貫した反応が見られるか検証することが不可欠です。
ご本人は表情、視線、体の動き、発声、生理的な変化など、実は多様なサインを発しています。それらを総合的に捉える必要があります。
これはとても難しく技術のいる仕事ですが、一朝一夕には読み取れなかったとしても、まずは「何らかのサインを発している」ことを理解することが大切です。
過去の行動パターンや、家族・支援者からの情報も参考になるかもしれません。多角的に本人の意思を探る努力が求められます。
・スイッチや意思伝達装置の活用
・安心できる環境設定
・十分な時間的配慮
など、本人が意思を表明しやすいように環境を整えることも支援者の重要な役割です。
どうしても意思確認が難しい場合の最終手段
本人の意思を直接確認することがどうしても困難な状況においてのみ、複数の関係者による合議にて支援方針を決定するとされています。
「本人の最善の利益」を最優先とする大原則を関係者全員が共有することが最も重要です。
過去の言動、
現時点で把握している本人の好み、
わずかな反応、
家族の意向、
専門職の意見。
さまざまな情報を丁寧に収集・分析し、本人の視点を最大限に想像・代弁する努力を尽くす必要があります。
閉鎖的な環境下では、とかく現場で支援にあたる職員主導、職員目線の方向性になりがちです。
本人のことを思っているような理由をつけて、実際には職員に都合の良い決定をしてしまうケースは多々見られます。
例えば
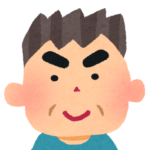
安全が最優先、事故起こってしまうことが1番ダメ!

危険行為が起こらないように、両手をミトンで拘束しましょう。
「事故が起こって1番困るのは本人」これは確かにその通りです。
だからと言って本人が明らかに嫌がっている拘束帯やミトンなどを安易に使用するのは、本人の人権を尊重していると言えるでしょうか?
正解は、事故が起こらない、かつ、本人が嫌がらない対応の仕方を考え続けることです。
その手段が見つからず、やむを得ず一時的に拘束的な対応があったとしても、すぐにでも外してあげられるように別の手段を考え続けるのが「意思決定支援」に基づいた対応です。
が、なかなか難しいのが現実のようです。

これも現場あるあるです。
あり過ぎて悲しくなってくるくらいあるあるです。
そういった事象を防ぐために、合議のプロセスは透明性の確保も重要です。
議論の過程、決定理由などを詳細に記録し、単なる多数決ではなく、具体的な根拠に基づいた判断であることを第3者が見てもわかるようにします。
第3者の意見を聞くことは重要です。

現場を知らない上司や第3者から「これはおかしいんじゃないか?」と言われるのは、現場の人間からすると正直モヤっとすることありますよね。
僕も何度も経験しているのでわかります。
しかし、無関係の第3者が「ん?」と思う部分、現場に深く入り込んでいると見えなくなる部分にこそ、意思尊重の侵害がおこりがちになるのは事実です。
「ぐぬぬ…現場の大変さを知らんのにキレイゴト言いやがって」という気持ちは一旦抑えて(それが難しいんですよね、わかりますよ!)、利用者の意思を尊重する姿勢が大切です。
合議による決定は、あくまであらゆる意思確認の努力を尽くした上での最終手段です!
そして、今出した結論に満足せず、新たな対応の手段や意思確認の方法をこの先も常に諦めず模索し続ける姿勢が求められます。
決定された支援方針は定期的に見直し、本人の状況変化や新たな情報に応じて柔軟に再検討する必要があるのです。
はっきり言って大変です。ですが、この姿勢があるとないとでは大違いです。
管理職層こそ真剣に取り組んでほしい
意思決定支援に取り組むには、現場で働くみなさんの努力・意識改革が不可欠です。
現場はとにかく忙しくて大変。
多忙な業務による時間的制約、長年の経験によるマンネリ化や固定観念などから支援が職員目線になっていくと、1番大切な本人の意思が置き去りにされてしまいます。
「本人の気持ちに寄り添う共感的な姿勢」
施設全体をそういう空気にしていく必要があります。
そのためには、管理職層が率先して意識改革に取り組み、現場の職員をサポートする体制を構築することに尽力してほしいところです。

残念なことに、現場を離れて久しい管理者層の上司が、もう現場の大変さを理解してくれなくなった…というのはよく聞く話です。
管理者層には管理者として、現場とは別のところで戦っていることは理解できます。
ですが、「現場に寄り添ってくれない言動が、運営管理に最も悪影響がある」。
そこは理解してもらいたいですよね。
この件についてはまた別の記事で詳しく扱いたいと思います。
意思決定支援への取り組みが不十分なまま現状を維持しようとすることは、施設運営にとっても多くのデメリットを生み出す可能性があります。
利用者主体の支援が提供できない = 質の低い意思決定支援を行っている施設、ということになります。
それが常態化し職員が何の疑問も持たなくなるのは大変危険です。虐待や権利侵害のリスクを高め、利用者の尊厳を損なうことにつながります。
虐待や権利侵害が明るみに出てニュースになったり、「尊厳に無頓着な施設」なんて悪評が立ったりしたらどうでしょう。管理者層にもデメリットしかないことは明白です。
Q:どちらの上司についていきたいと思いますか??

意思決定支援をちゃんとやっていこう!
めんどくさいけど、監査にバレたら減算されちゃうから…
みんな、問題だけは起こしてくれるなよ。

意思決定支援をちゃんとやっていこう!
利用者の人権を尊重し、より良い暮らしを支えるのが我々の責務だ!
困った時はどんなことでも相談してくれ!
暑苦しくなく、気楽に働けるのはXさんの施設かもしれません。
でも利用者やご家族から信頼され、将来安泰なのはどう考えてもYさんの施設。ここまでお読みいただいた方ならわかってくださると思います。
ですから組織上層部の方達にこそ、質の高い意思決定支援が行われるための旗振りをしていただき現場の士気を高めていただきたいのです。
法令遵守や監査対策といった側面だけしか見ていない事業所は大変危険です。
改革はとても大変
…と、ここまでお読みいただいて

偉そうなこと言って
そういうアンタはさぞかし立派な意思決定支援をやってきたんだろうな?
と思われるのは当然ですよね。

いえ、全然できていませんでした。
僕自身、入職したての若手の頃は決められた業務をいかに早くこなすかに躍起になっていました。
ここで嘘をついてもしかたないので正直に白状しますが、「業務の効率化」を「利用者さんへの人権的配慮」よりも優先していた時期がありました。
このままではヤバいな、と思うようになったのは主任になってからでした。
・職場全体がそういう風潮だった。
・とにかくやることが多過ぎて忙しいからしかたがない。
これらは全て言い訳です。若い頃はそう自ら言い聞かせることで、利用者と向き合えない自分を正当化していました。
こんな言い訳をさせないために、職員の意識改革と同時に、業務改善・職場システムの見直しが絶対に必要になります。
一度身についた固定観念や習慣に変化をもたらすのはとても大変です。
僕も主任就任以降いろいろとトライしては挫折してきました。
大きな改革にあたっては、現場の人間には決定権がない職場システムの見直しも必要になってきます。
なので、繰り返しますが、現場より1段上の管理者層の協力が不可欠なのです。
また、変な固定観念が身についてしまう前の新人教育もとても重要です。
改革と同時進行で、いやむしろ「新人教育こそ意識改革の柱」とまで言っても過言ではありません。
意思決定支援はとても大変で時間のかかる仕事です。
がんばってそれに向き合っている先輩と、巧妙に回避してうまいことやっている先輩。
新人に対して影響力があるのは後者です。これは経験上断言できます。
悲しいけど人間は楽な方を選ぶ生き物なんですね。
ですから悪い影響を受ける前に、新人さんに利用者の人権を尊重する支援がいかに大切か、しっかり教育することは大切です。
逆に、そういうしっかりとした価値観を持った新人さんが増えてくれば、徐々にワルい先輩のほうが肩身が狭くなり考え方をシフトせざるをえなくなります。
新人教育は、それ自体が全体の意識改革のいち手段としてとても有効なんです!!
ちなみにこれは、僕が離職前に関わった最後の新人さんへの指導で、確かな手応えのあったアプローチです。気づくの遅過ぎ!
自分は志半ばで戦線離脱してしまいとても残念ですが、今現場でがんばっておられる支援員の皆さんに是非とも伝えておきたいことのひとつです。
まとめ
意思決定支援は、障害のある方が自分らしく生きるための基盤となる、極めて重要な支援です。
特に、意思を表明することが難しい方への丁寧なアプローチは、支援者の専門性と倫理観が問われる領域で、安易な判断は絶対に避けないといけません。
当然といえば当然なのですが、この当然のことができているなら、今後の報酬改定がどんなに厳しくなっていこうと何の問題もありません。
できていないなら、早期に手をうつべきです。
いま真剣に意思決定支援に取り組むことは、利用者本人の尊厳を守り、より質の高い、個別化された支援を提供するための責務です。
それは、利用者、支援者、そして事業所全体の幸福につながる道です。
未来の障害福祉をより良いものにしていくための重要な一歩になると思います。
お読みいただきありがとうございました。