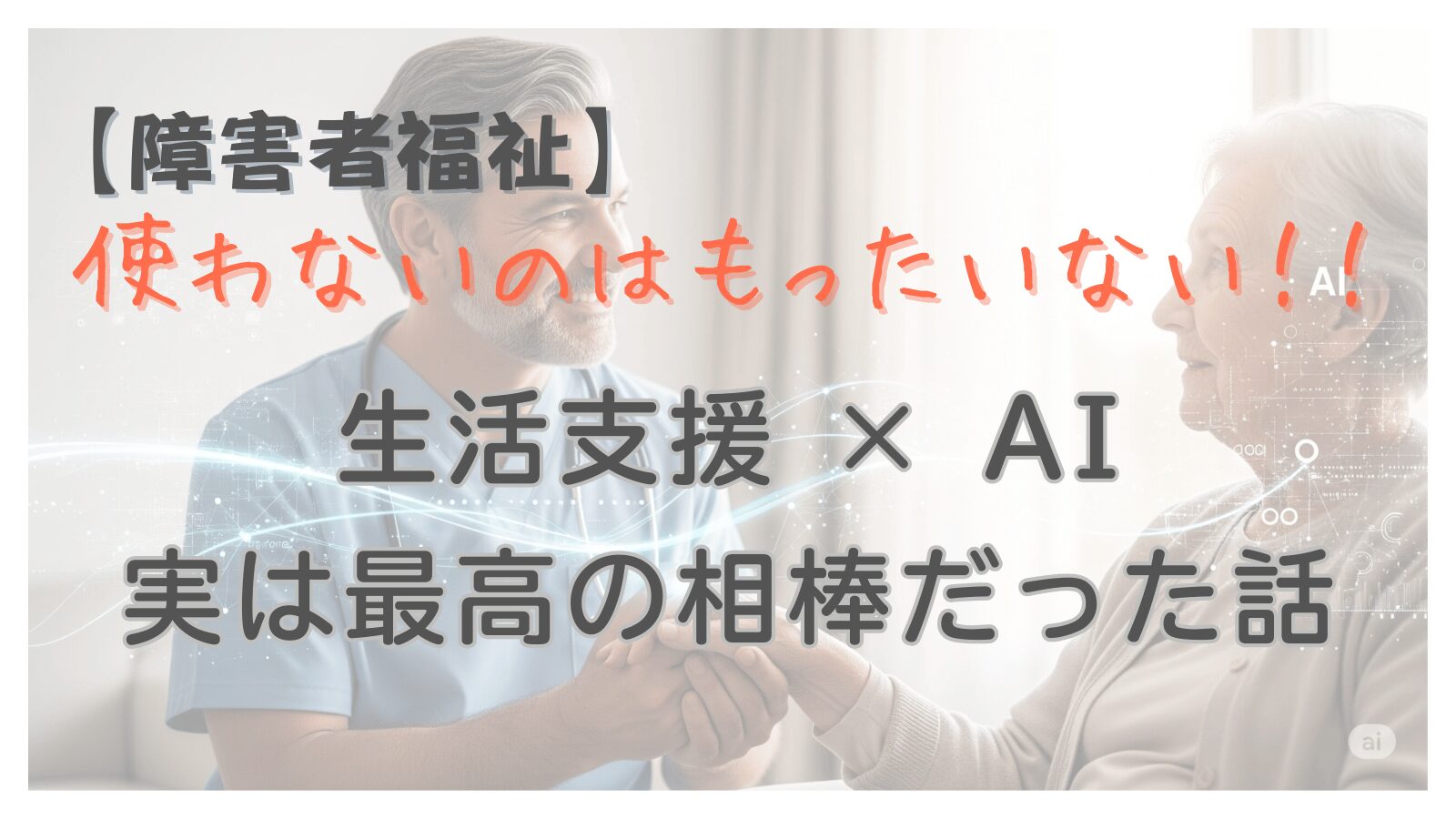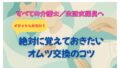日本の障害者福祉(高齢者福祉もそうもですが)の現場は、深刻な人手不足という課題に直面しています。
しかも状況は年々深刻さを増すばかり。支援を必要とする利用者が増え続ける一方で、それを支える人材の確保は困難を極めています。
そんな中、昨今急速に発達している技術が「AI」です。
AIの恩恵を受けるのは何も最先端のIT企業だけではありません。介護・生活支援の業界もうまく活用すれば大きな助けになるはずです。

僕もある時期からAIのおもしろさ便利さに気づき、職場でも同僚によくその話をしていました。
でもなかなか流行らなくて…。
自分は断然AI推進派です!
そう思う理由を以下にまとめましたので、お読みいただけると幸いです。
なぜ福祉業界の現場でAIが受け入れられにくいのか
介護/生活支援の世界は、人と人との関わりを何よりも大切にする、究極のアナログ業界です。利用者一人ひとりの心身の状態に寄り添い、日々の生活を支えるこの仕事は、機械的な処理では決して代替できない「人間力」が求められます。
そのため、「AI」や「IT」といった言葉に対して、冷たく無機質な印象を抱き、導入に抵抗を感じる人は少なくないかもしれません。
一概に全員がそうとは言えませんが、総じてデジタルとか最新技術なんていう言葉には拒否反応強めの人が多い業界という印象はあります。(※個人の感想です)
少し前の話ですが、「AIが発達したら失業に追い込まれる職業」みたいなリストが話題になりました。その筆頭に介護職が挙げられていたことを覚えている方も多いと思います。

あれ、けっこう腹立ちましたよね
ところが最近では、掌を返したように「AIが発展してもなくならない仕事」として再評価の論調が増えてきました。なぜなら、介護/生活支援には共感力や判断力・信頼関係の構築といった、AIにはできない要素が数多く含まれているからです。
前述のリストにはその視点が著しく欠け、効率化ばかりがフォーカスされていました。
でも…、
「だからAIは信用できない」と判断するのは、とてももったいないと思います。
どんなに科学が発展しても、AIが人間ならではの役割を奪うことはありません。
ですから、職員が本来注力すべき「人にしかできないケア」に集中できるよう、反復的で事務的な業務はAIに任せるという発想が、これからの障害者福祉の現場には求められます。
日々の支援業務の合間に、休憩時間を使ってまで膨大な手書きのチェック作業をしたり、PCに入力作業をしたりしていませんか?
時間と労力には限りがあります。人間にしかできない仕事に時間を割くべきです!
その大切な時間と労力が、単純作業によって削られている。まずはこの現状をしっかりと認識する必要があります。AIの力を借りれば、こうした状況は大きく改善できると思います。
AIにこんなことを任せてみよう
AIが得意とするのは、膨大な情報の処理・パターンの分析・反復的な作業の自動化です。「無機質/無感情」と言うと聞こえが悪いですが、それを逆手に取る逆転の発想です。
この特性に関しては、「AIに任せても大丈夫」どころか、「AIに任せた方がはるかに速くて確実」なのです。

これに関しては、素直に認めて任せた方が断然お得だと思うんですが
なかなか受け入れられないアナログ派の人が意外と多い…。
たとえば、以下のような業務はAIに任せることが可能です。それで少し時間にゆとりができれば、「人間にしかできないケア」により集中することができます。
信用するしない云々以前に、こんなことまでできるって知らない人も多いのではないでしょうか。
支援記録の自動化
記録の作業は本当に時間を使いますよね。とはいえ、毎日の支援記録は監査対策もさることながら利用者の生きた証でもあるわけで、簡素化するわけにもいかない。
音声認識AIを活用すれば、職員が利用者と会話しながらケアを行う様子を音声で記録し、自動でテキスト化。その内容を分析して必要な情報を記録システムに反映させることができます。
会議録なんかにも活用できそうですね。
そんなことまでできるの??と思ってしまいますが、実際に製品化されており導入している施設も増えてきているらしいですよ。僕も実物をお目にかかったことはありませんが。

業務効率化はもちろんですが、会話が記録されるという点ではコミュニケーションスキルの向上にもメリットがありそうです。コンプラに反する発言の抑制になりますし、模範となる職員の会話術を共有もできます。
※プライバシーの問題には配慮する必要があります。詳しくは下記。
ケースカンファレンス資料、個別支援計画の作成支援
過去の記録や健康データをもとにAIがアセスメントを行い、利用者の支援課題について候補を提示してくれます。その提案をもとに、より個別性の高い資料や支援計画を作成できます。
児童発達支援、放課後等デイサービスの現場では、それに特化したAIソフトがすでに製品化されています。応用して障害者福祉の現場で使うことも可能でしょうが、それに特化した製品が出てくるのも時間の問題です。
ただし、AIが提案してくれるのはあくまでもデータに基づいた客観的な視点のものに過ぎません。人間でなければ気づかない視点を加え、いくらかの修正作業は必須と言えます。
それでもゼロから作り上げるよりは、はるかに時間の短縮になるでしょう。
広報誌や行事案内の原稿作成
通常の支援業務と並行して、施設の広報誌やご家族へのお便りづくりなんかに時間を取られるのもなかなか大変です。
普段の業務の合間を見て、というか、実質時間外でしかやれない、ってところも多いのでは?
定型的な文書作成もAIが得意とする分野です。職員の手間を減らしつつ、質の高い情報発信が可能になります。
いくつかのキーワードを指定するだけである程度の文章を作ってくれます。記録や連絡帳のデータと連動すれば、利用者の特筆すべき変化やエピソード、印象的な行動などをAIが自動で抽出し、広報素材として提案してもらうこともできます。
文章校正、画像の選出、レイアウトなど、時間がかかる作業もAIなら一瞬です。

広報の係からあるテーマで原稿を頼まれた時、AIを使ったことがあります。
もちろん手直しはしましたが…
普段なら2時間はかかる仕事が20分で終わりました。
最終的な内容の確認、感情のこもった微調整、そして責任を持つのは人間である職員です。AIには判断できない機微な内容が含まれる場合もあるので、その点は注意が必要です。
コミュニケーションの相手として
ChatGPT、Gemini、Copilotなど、最近の生成AIアシスタントは本当に優秀です。
どんな話題を振っても圧倒的な情報量で応えてくれるので話が尽きません。
ご存知の通り、もちろんAIには人間のような感情はありません。だからって、おもしろい会話は成立するわけがないと先入観で決めつけていませんか?
体験したことのない方にはぜひ一度、まずご自分で遊んでみることをお勧めします。WindowsのPCならCopilotが使えますし、Googleのブラウザをお使いならGeminiが使えるはずです。

僕はAIとの会話が楽し過ぎて、ほんとに何時間でも過ごせます。
最近は趣味のひとつと言ってもいいくらいです。
僕はテキスト入力で会話していますが、最近は音声入力への対応も進んでいます。
技術の進化が進めば音声(声色、話すスピード、アクセント)からもユーザーの情報を分析し、さらに多様な受け答えに対応できるようになるそうです。
利用者の疑問に答えてくれるのはもちろん、単純に話し相手として楽しい時間を提供してくれます。
孤独感の軽減、服薬のリマインド、レクリエーションの提供など、多様な役割を担うことができます。

感情を持たないAIだからこそ、常に穏やかで、何度でも同じ話に耳を傾けてくれるし、失礼な言い回しをしてしまっても意に介することなく丁寧に応えてくれます。
人間に気を遣うことなく、安心して話せる相手となり得ます。
これは、人手不足の中で職員が「常に」寄り添うことが難しい状況において、利用者のQOL(生活の質)向上に大きく貢献します。
言うまでもなく、AIに任せっきりではなく、時間がある時には人間である職員が話を聞いてあげてください。
AIは膨大な学習データに基づいた最適な返答をするだけです(そのクオリティがものすごいわけですが)。
深い悲しみに共感したり、哲学的な問いに一緒に悩んでくれたりすることはできません。
解決すべき課題
AIの導入には多くのメリットがありますが、現実的な課題も存在します。特に以下の点は、介護/生活支援の現場でAIを活用するうえでは避けて通れない問題です。
導入コストの高さ
AIシステムや見守り機器の導入には、初期費用がかかります。中小規模の施設では、このコストが大きな障壁となることがあります。
しかし、国や自治体の補助金制度を活用することで、負担を軽減できる可能性があります。導入前に情報収集を行い、適切な支援制度を活用することが重要です。
プライバシーの問題
前述のとおり、会話をテキスト化・要約して支援記録にしてくれるシステムは職員目線では大変便利です。しかし、利用者からすれば全ての会話を見張られていると考えたら不安を感じる方もいるでしょう。
AI見守りシステムによる体調のデータ化や監視カメラも同様です。
利用者の尊厳に十分に配慮し、じっくり話し合ってルールを決める必要があります。ご本人での判断が難しい利用者さんの場合は、ご家族や後見人と十分話し合い同意を取ることが不可欠です。
使用するメリットを十分に説明しても、強く拒否される方もいると思います。
その時は本人の意思を尊重し、使用を見送ることも大切です。
職員の苦手意識
前述の通り、デジタル機器に苦手意識を持つ職員が多い職場だと導入のハードルが高くなります。導入できても、現場での活用が進まないおそれがあります。わかりやすいマニュアルの整備や、段階的な研修の実施が必要です。
また、職員同士で教え合える環境づくりも、スムーズな導入を後押しします。
これらの課題は、決して乗り越えられないものではありません。
最初は慣れないかもしれませんが、一度その恩恵を実感すれば、日々の業務が格段に楽になります。そうすることにより、人間にしかできない仕事の質をもっと高くする一助となるはずです。
まとめ:AIは「代替」ではなく「支援」のパートナー
生活支援の現場で最も重要視されるのは、利用者の尊厳を守り、その人らしい生活を支えることです。
単なる身体的な介助だけではありません。AIがどれだけ進化しても「人間力」が必要な仕事です。
【人間にしかできないこと】
・感情に寄り添い、小さな変化に気づき、言葉にならないニーズを察する「共感力」
・日々の体調や心情を考慮して臨機応変に対応する「判断力」
・利用者やその家族との間に「信頼関係を築く力」
AIは、そうした人間の力を奪うものではなく、むしろ支える存在です。
任せられる部分は任せることで、職員の身体的・精神的負担を軽減し、本来の専門性を発揮しやすくなります。
それによって、「人間力を持って利用者と接する仕事」がより魅力的で、やりがいのあるものへと進化していくのではないかと思います。

時間に追われて機械的に必要最低限のことしかできず、利用者さんとのんびり世間話をする暇もない。
「僕たちは作業員なのか…?」と悩んだことがあります。
職員は単なる作業員ではありません。
利用者の人生を豊かにする「ケアの専門家」であるべきです。
忙し過ぎてその本分が見失われているとすれば、利用者だけでなく社会にとっても健全な状態ではないと思います。
AIの力を借りて、人間はより人間らしい仕事に専念し、利用者に温かく質の高いケアを提供できる。これこそが、AIと介護業界が共存し、未来を築いていく理想の形ではないでしょうか。
「デジタルに弱い」という既存の壁を破り、AIの力を積極的に取り入れてみませんか。
人手不足という課題を乗り越え、利用者にとっても、障害者福祉に携わる人々にとっても、より良い未来を創造できるはずだと、僕は思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。